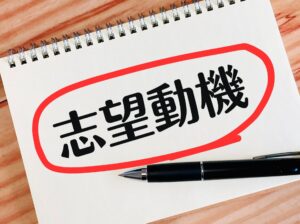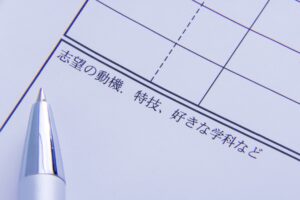「仕事に就きたい!」と思った時に、まず必要になるのが、履歴書です。
履歴書は、氏名・住所・学歴などの基本情報を伝える応募書類であり、採用担当者が書類選考の通過を判断するための審査書類でもあります。
正しい作成ルールに沿って履歴書を作成すること、そして履歴書の内容を通してしっかりと採用担当者に自分の熱意を伝えることが、書類選考を通過するためには非常に重要です。
今回は、書類選考の通過につながる履歴書の書き方をご紹介していきます。
正式なビジネス文書として大切な履歴書を、効率よく作成できるおすすめの書き方や、作成時の注意点などを詳しくご紹介していきますので、最後までご覧ください。
手書き作成?パソコン(スマホ)作成?気になる履歴書の書き方

まず履歴書の書き方としては、「手書き」、もしくは「パソコンやスマホのブラウザを活用した作成法(履歴書作成サイトの利用)」と、2つの方法があります。
特に「手書きの履歴書に限る」などの指定がない場合は、どちらの書き方で作成しても問題ありません。
履歴書のおすすめな書き方はパソコン作成!
企業から指定がない場合は、パソコンやスマホを用いて履歴書を作成することをおすすめいたします。
手書きよりもパソコン作成をおすすめする理由は、3つあります。
まず1つめは、履歴書を作成する時間を大きく短縮できることです。
手書きで履歴書を作成する場合、下書きと清書で2度の手間がかかる上に、修正テープ等の使用ができないため、間違えた場合は新しい用紙に一から書きなおす必要があります。
しかしパソコンやスマホのブラウザを使って作成する場合は、文章の推敲や誤字脱字の訂正も、キーボード操作で簡単に行うことができます。
複数の企業に応募する場合も、氏名・住所・学歴などの基本情報を履歴書作成ツールに登録しておくことで、使い回すことが可能なので、履歴書作成の時間を短縮することが可能です。
2つめは、採用担当者に対して文章の内容を伝えやすいということです。
手書きで履歴書を書く場合、字の大きさを揃えて、丁寧な楷書体で作成する必要があります。
文字に強いクセがある場合などは、採用担当者が内容を理解することが困難になってしまい、書類選考の結果に大きく影響します。
パソコンやスマホで作成したものであれば、採用担当者にとっても読みやすく、また内容がダイレクトに伝わるので、書類選考の通過につながるので、履歴書の書き方としてはブラウザの使用がおすすめです。
3つめは、応用性の高さです。
近年では履歴書の提出方法として、郵送や持参以外にも、メール添付や専用サイトへのアップロードを指定されることがあります。
履歴書をパソコンやスマホで作成し、データを保存しておくことで、印刷とデータ送付のどちらにも対応がしやすく、利便性が高くなります。
また「面接前のスキマ時間に、履歴書に書いた内容を確認したい」という時も、保存してデータをスマホで確認することができるというメリットもあるので、就職活動や転職活動をスムーズに上で、パソコンやスマホのブラウザでの作成がおすすめです。
ブラウザを使った履歴書の書き方

パソコンやスマホのブラウザを用いて履歴書を書く時に、必ずチェックしておきたいポイントを5つ紹介します。
正しい書き方で作成した履歴書は、書類選考の通過につながるので、しっかりと確認した上で丁寧に作成していきましょう。
用途にあったテンプレートを用いる
履歴書を書く上で大切なのは、自分に合ったテンプレートを用いることです。
具体的には、「パート・アルバイト用」、「新卒用」、「転職用」の中から、自分の目的に合ったテンプレートを選ぶことが大事になってきます。
例えば、パート・アルバイト用であればシフトの希望欄が設けられていたり、新卒欄であれば自己PRや学生時代に力を入れて取り組んだことの記入欄が大きく設定されていたりします。
自分の希望する採用形態に合わせたテンプレートを用いることで、1枚の用紙スペースを有効に活用しながら自分の熱意をアピールすることにつながるので、必要に応じて記入項目をカスタマイズしながら履歴書を作成していきましょう。
誤字や脱字に注意する
ブラウザを活用した書き方に限った話ではありませんが、履歴書を書く上では誤字脱字に注意が必要です。
漢字の間違いやタイプミスなどが目立つ履歴書は、採用担当者に「ミスの多い人物の可能性がある」、「社会人としての常識が不足している可能性がある」という印象を与えかねません。
特にブラウザで作成した場合は、キーボードの予測変換機能によって思わぬ誤字脱字が生じている可能性があるので、細心の注意を払って作成してください。
また、履歴書は正式なビジネス文書として扱われます。
十分なパソコンスキルを有していたとしても、文字を太くする(太文字)・アンダーラインを入れる・文字の色を変えるなどといった装飾は、一切不要です。
必要な項目を入力し終わったあとは、誤字脱字のチェックと、ビジネス文書として正しい書式になっているかを確認しなおすことをおすすめいたします。
年号と日付を確認
ブラウザで作成するタイプの履歴書は、生年月日を入力すると自動的に、学校の卒入学年度を計算してくれる便利なシステムが搭載されているケースがあります。
自動計算は非常に便利ですが、改めて自分の目で間違いがないか確認することを心がけてください。
取得資格や職歴を自分で入力する際は、年号が一致しているか(西暦と元号が混同していないか)を必ず確認する必要がありますので、こちらも合わせてチェックしましょう。
提出前には、年号の表記と合わせて、履歴書の提出日欄の確認も必須です。
ブラウザで履歴書を入力した場合、履歴書の作成日が、入力日に設定されてしまうので、提出日や送付日の日付に書きなおしてから、提出してください。
添え状や職務経歴書も同じフォントで作成する
郵送で履歴書を送付する場合は添え状の添付が、転職活動の場合は職務経歴書の添付が、それぞれ必要になります。
履歴書をパソコンやスマホのブラウザで作成するのであれば、添え状や職務経歴書も同じ履歴書作成サイトを利用することで、送付書類に統一感が出ます。
見栄えよく揃った書類は、「ビジネススキルや社会人としてのマナーが十分な人物である」、「職務上必要なパソコンスキルが身についている」と、採用担当者に好印象です。
自己分析と企業研究をしっかりと行う
履歴書を作成する上で大事なのが、自己分析と企業研究です。
履歴書を正しい書き方で作成しても、自己PRが不十分であったり、応募先の企業に対してどのような貢献ができるのかという部分が伝わらなかったりすると、採用担当者に熱意が伝わりません。
基本情報はブラウザに入力したものを使いまわすことで時間を短縮して、しっかりと自己PRや志望動機を考える時間に充当することをおすすめします。
就職活動や転職では、複数の企業に対して履歴書を送付することが多いですが、必ず応募企業ごとに自己PRや志望動機は調整して、熱意を伝える必要があります。
使いまわす部分と、応募先に合わせてこだわる部分を書き分けることが、効率のよい履歴書作成と書類選考の通過につながるのでおすすめです。
履歴書が書けたあとにすること

ブラウザを活用して履歴書や添付書類が作成できたら、提出まではあと一息です。
履歴書作成サイトを使用した際に見逃しやすいチェックポイントを、3つご紹介します。
証明写真のアップロード
履歴書には、証明写真を貼り付けるスペースが指定されています。
募集要項に「顔写真不要」の文言がない場合は、必ず証明写真を貼付する必要がありますが、「印刷してから貼り付けよう」と考えていて、うっかり顔写真を忘れて提出する方が非常に多いです。
対策としては、証明写真をデータで準備しておくことです。
写真館はもちろんのこと、近年ではスピード写真機でも撮影した顔写真をデータ化できる機能が備わっているものがあります。
せっかくブラウザで履歴書を作成するのであれば、証明写真もデータでアップロードしておき、証明写真の貼り忘れがないように対策をしておくことがおすすめです。
なお証明写真は、撮影から3ヵ月以内のものしか使用することができませんので、就職活動が長期間にわたる場合は注意してください。
印刷サイズ・ファイル形式をチェック
郵送もしくは手渡しで履歴書を提出する際は、A4サイズ(A3用紙二つ折り)、もしくはB5サイズ(B4用紙二つ折り)のいずれかの用紙サイズが一般的です。
用紙サイズの指定がない場合はどちらのサイズで提出しても問題はありませんが、例えば「自宅プリンタの都合で、A4用紙2枚で提出する」といったことは避けて、コンビニ印刷等を利用してください。
メール添付やサイトへのアップロードという形で履歴書を提出する場合は、「PDFファイル」に変換してから送付する必要があります。
WordファイルやExcelファイルで送付してしまうと、改ざんが容易に可能なため、正式なビジネス文書としては不適格です。
必ず一度、加筆や訂正ができないPDFファイルに変換して送付してください。
迷ったら「プロ」に相談
履歴書をブラウザで作成する過程で、「これで合っているのかな」と不安に感じたり、「なかなか書類選考を通過しないけれど、なぜだろう」と悩んだりすることは、珍しくありません。
そのような場合は、就職や転職活動のプロに相談し、履歴書の書き方のアドバイスをもらったり、自分の適性に合った業界や求人を紹介してもらったりすることで、現状を打破できる可能性が高まるのでおすすめです。
特にブラウザを用いた履歴書作成サイトから、オプション機能として履歴書添削や就活アドバイスを申し込むことができると、効率良く履歴書の書き方をアップデートすることにつながりますので、是非一度お試しください。